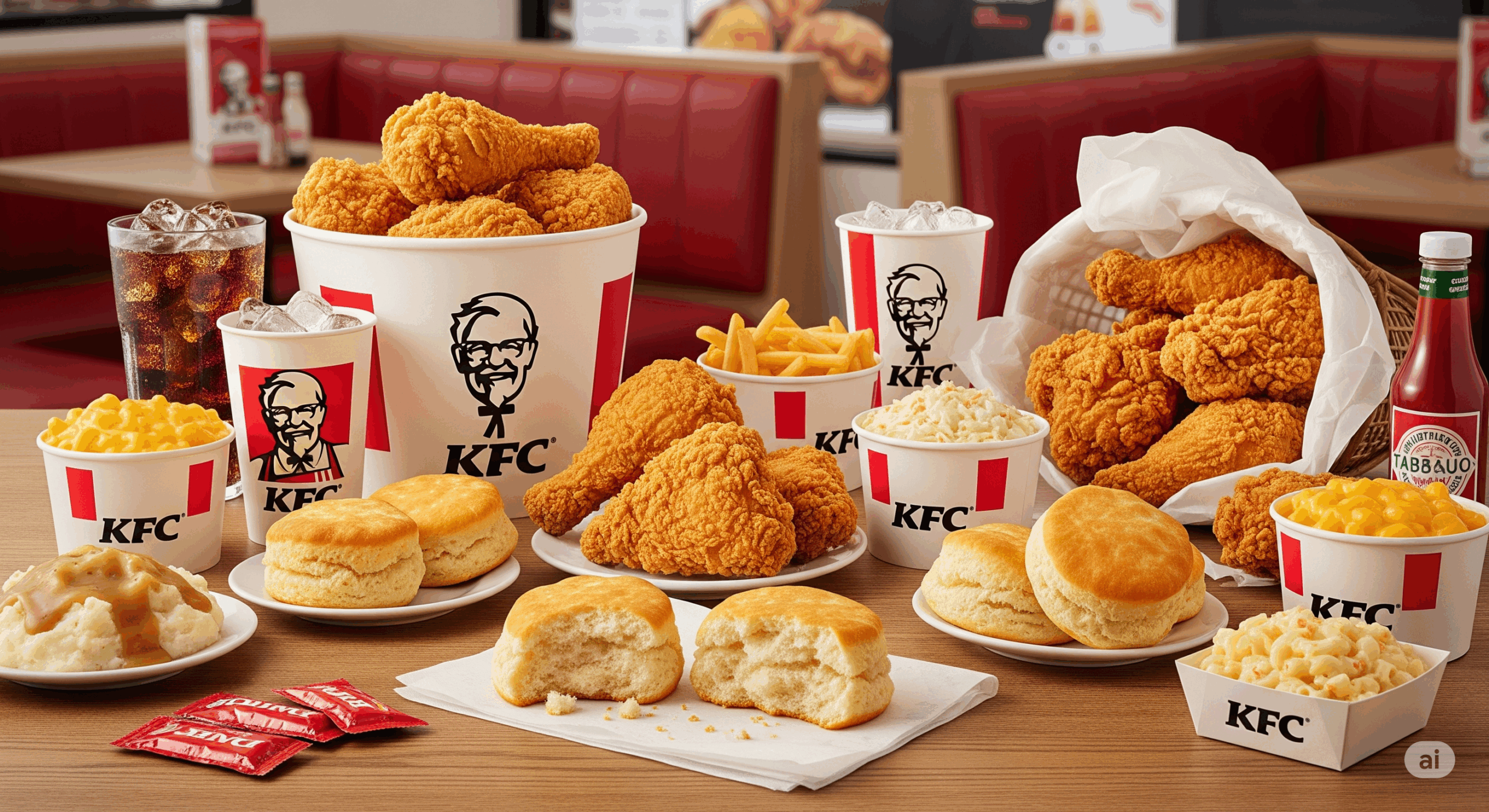※本記事には 広告(Amazonアソシエイト含む)が含まれる場合があります。
※当記事は公開情報をまとめた考察記事です。記載内容は執筆時点で確認できた情報に基づきます。
ケンタッキーのフライドチキンを心ゆくまで楽しみたい!そんな方のために、本記事では2025年最新のケンタッキー食べ放題情報をまとめています。「どの店舗でやっているの?」「料金はいくら?」「予約は必要?」といった疑問にすべてお答えします。
食べ放題を実施している「KFCレストラン」店舗一覧(2025年最新)
残念ながら、食べ放題は全国すべてのケンタッキーで楽しめるわけではありません。現在、常設で食べ放題を実施しているのは、全国でわずか2店舗のみです。これらは「KFCレストラン」という特別な形式で営業しています。
1. ららぽーとEXPOCITY店(大阪府)
- 住所: 大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY 1階
- 営業時間: 11:00~22:00(L.O. 20:30)
- 料金: 曜日や時間帯によって異なります。
- メニュー: オリジナルチキン、ビスケット、パスタ、カレー、サラダ、デザート、ドリンクバーなど。
- アクセス: 大阪モノレール「万博記念公園駅」から徒歩約2分。
2. 小野店(兵庫県)
- 住所: 兵庫県小野市中町388-1
- 営業時間: 11:00~22:00(L.O. 20:30)
- 料金: 曜日や時間帯によって異なります。
- メニュー: ららぽーとEXPOCITY店と同様のラインナップです。
- アクセス: JR加古川線「小野町駅」から徒歩約10分。
補足: 上記2店舗以外にも、期間限定で食べ放題イベントが開催されることがあります。最新情報は必ずケンタッキー公式サイトやSNSで確認しましょう。
【料金体系】ランチとディナー、どっちがお得?
KFCレストランの料金は、ランチタイムとディナータイム、そして平日と土日祝日で異なります。ここでは、おおよその目安をお伝えします。
| 区分 | ランチ(11:00~17:00) | ディナー(17:00~22:00) |
|---|---|---|
| 大人 | 2,000円台 | 3,000円台 |
| 小学生 | 1,000円台 | 1,000円台 |
| 幼児 | 500円以下 | 500円以下 |
| 3歳未満 | 無料 | 無料 |
※料金は店舗によって異なる場合があるため、あくまで目安です。
食べ放題で楽しめるメニューは?
食べ放題では、オリジナルチキンを始めとする定番メニューの他に、通常店舗では見られない限定メニューも楽しめます。
- メイン: オリジナルチキン、フライドポテト、パスタ、カレー
- サイドメニュー: コールスロー、ビスケット、サラダバー
- デザート: ソフトクリーム、ゼリー、フルーツ
- ドリンク: ドリンクバー
KFCレストランの食べ放題を最大限に楽しむための攻略法
せっかく行くなら、食べ放題を最大限に楽しみたいですよね。ここでは、筆者の経験に基づく攻略法をご紹介します。
- 最初の1皿は少量に: いきなりお皿いっぱいに盛るのではなく、まずは少量を取って味を確かめるのがおすすめです。特にオリジナルチキンは揚げたてが一番美味しいので、少量ずつこまめに取りに行くのがおすすめです。
- 部位の違いを楽しむ: ケンタッキーのフライドチキンには5種類の部位(サイ、ドラム、リブ、ウイング、キール)があります。それぞれの味や食感の違いを楽しんでみてください。
- サイドメニューで味変: ビスケットやサラダバーを上手く活用して、フライドチキンばかりで口が重くなった時に味を変えるのがおすすめです。
知っておきたい!ケンタッキー食べ放題の注意点とよくある質問
スムーズに利用するために、以下の点も事前に把握しておきましょう。
- 制限時間は90分: ほとんどの店舗で90分の時間制限が設けられています。
- 予約がおすすめ: 週末や祝日は大変混み合います。スムーズに入店するためにも、公式サイトから事前予約をすることをおすすめします。
- 持ち帰り不可: 食べ放題で残した料理の持ち帰りはできません。食べられる分だけ取るようにしましょう。
- 情報の最終確認: 料金や営業時間、メニュー内容は変更される可能性があります。必ず訪問前に公式サイトで最終確認してください。
まとめ|お得にケンタッキー食べ放題を楽しもう!
ケンタッキーの食べ放題は、一部の店舗でしか体験できない特別なサービスです。料金やメニュー、利用方法を事前に把握しておくことで、より一層楽しむことができます。
ぜひ、この記事を参考に、ケンタッキーのフライドチキンを心ゆくまで味わってみてください!
ハル(大阪府在住)
物流機器メーカーに勤務する 40 代サラリーマン。調達部門で社内外 300 社を横断するサプライチェーンの改善プロジェクトを担当しつつ、終業後と週末にニュース考察ブログ 『報道の裏側』 を運営しています。
「専門外の人でも 10 分で“その話題のツボ”がつかめる解説」を届けることを目指します。